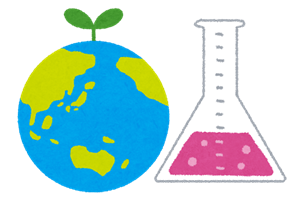1.化学物質発達期曝露による神経影響の解析
医療や産業に使われている化学物質の中には、胎児期や乳幼児期の曝露により、成長後の行動異常を引き起こすものが少なからず存在します。例えば、妊娠中に抗てんかん薬バルプロ酸(VPA)を服用すると、児の知能指数(IQ)低下や自閉症のリスクが上昇することが報告されていますし、電気機器の絶縁油として使われたポリ塩化ビフェニル(PCBs)の胎児期曝露は生後の記憶・学習障害や社会行動の異常の原因となることが示唆されています。このような化学物質の神経影響については、ニューロンの電気的活動や移動(migration)に焦点が当てられ研究されてきましたが、メカニズムの大部分は未解明です。
神経回路の連結部であるシナプスは、発生の過程で過剰に形成され、ミクログリアという脳内の免疫担当細胞によって不要なものが刈り込まれる(貪食される)ことが知られています。つまり、発達期のミクログリア活性が異常(過活性化或いは抑制)となると、異常な神経回路網が形成されると考えられます。
私たちは、妊娠中にバルプロ酸を摂取したマウスの解析を進めています。妊娠中期に一度だけバルプロ酸を投与したマウスから産まれてきた仔は、成長後に空間認知機能の障害や社会性の異常など、発達障害様の行動を示しました。このような仔の海馬(学習行動などに関与する脳部位)では炎症が生じており、その神経細胞の興奮状態が異常に高まっていました。バルプロ酸を妊娠期に投与したマウスから産
まれてきた仔の海馬で発現が変化する遺伝子を網羅的に調べたところ、炎症性ケモカインの一つであるCCL3 の発現が上昇していることを突き止めました。CCL3 の受容体であるCCR5 を阻害するマラビロク(ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症治療薬)を授乳期に投与したところ、神経細胞の興奮を鎮めることができ、成長後の発達障害様の行動を示さなくなりました。従って、脳内ケモカインCCL3はバルプロ酸による発達障害の原因分子であると考えられます(Ishihara et al. J Neuroinflam. 2022)。

脳内のケモカインの役割には不明な点が多いのですが、農薬やダイオキシン類など、様々な化学物質の認識曝露により、脳内でケモカインが増えることが分かってきました。私たちは、脳内ケモカインで化学物質による発達障害がある程度は説明できるのではないかと考え、研究を継続しています。また、当初、ミクログリア-ニューロンの細胞間相互作用に着目していましたが、ミクログリア-オリゴデンドロサイト間の情報伝達が関わっているような結果が得られており、面白い成果が得られつつあります。
2. 環境中微粒子の生体影響の解明
2-1. 大気中マイクロプラスチックの健康影響の解明
直径5 mm以下のプラスチック片はマイクロプラスチック(microplastics: MPs)と呼ばれ、その多くは海洋に存在し、生物の誤食など生態影響が生じることが明らかになりつつあります。一方、MPsは大気中にも一定量浮遊しており、繊維状や球状、ポリプロピレンやポリエチレンテレフタレートなど、様々な形状や材質のMPsが観察されます。大気中MPsの主な標的は、気管支や肺などの呼吸器系、さらに常に大気に露出している皮膚であると考えられますが、その健康影響はほとんど明らかにされていません。私たちは、新しいポリエチレンテレフタレートがほぼ毒性を示さないのに対し、太陽光によって劣化したポリエチレンテレフタレートが呼吸器毒性を示すことを明らかにし、プラスチックの光劣化が毒性と密接に関連することを示しました(Ishihara et al. Toxicol Sci. 2025)。現在、ポリプロピレンやポリエチレンなど、他のプラスチック素材、およびナノプラスチックへと研究を展開しています。また、環境モデルを導入し、どこでどれくらいプラスチックが劣化を受けるかをシミュレーションすることにより、新しいリスクアセスメント法の開発も進めています。

2-2. 屋外環境を模した培養チャンバーシステムの開発と新規素材のスクリーニング
屋外において皮膚は太陽光、大気中微粒子および環境温度に曝されます。従って、屋外環境の皮膚影響をin vitroで調べるためには、これら3つの環境因子を曝露できる培養系の開発が必要でした。そこで、私たちは、人工太陽光を照射しながらPM2.5を気相曝露し、かつ培養温度を可変とするチャンバーシステムを開発しました(特願2024-207105)。現在、チャンバーシステムの最適化を進めると共に、新規素材のスクリーニングを進めています。
2-3. 極狭空間の空気室評価を指向したインピンジャーシステムの開発
屋内は屋外に比べて採取できる空気量が圧倒的に少ないため、空気質を収集し、成分を分析することは技術的に極めて難しい状況です。また、外気流入により、空気量が少ない屋内環境は影響を受けやすい特徴があります。一方、ヒトは屋内で過ごす時間が長く、屋内環境の健康リスク評価は重要となってきます。私たちは、独自に開発したインピンジャーとバイオアッセイを組み合わせ、狭い空間の空気室を評価できる手法を開発しました(特願2024-193491)。現在、この評価手法を応用して、様々な極狭空間の評価を実施しています。
3. 環境温度の変動に対する適応機構の解明
温度は動物の行動や細胞の増殖、酵素活性などあらゆる階層の生命現象に多大な影響を及ぼします。気温や水温といった地球上の環境温度は季節の移り変わりや日内で変動しているため、生物は生存のために環境温度の変動に対する適応システム(夏眠や冬眠などの休眠ならびに植物での糖蓄積など)を備えています。興味深いことに、温度適応システムは細胞単位においても観察され、例として低温誘導遺伝子の発現や概日時計の温度補償性が挙げられます。これまでの研究により、各温度適応システムにおいて重要な分子がわかってきましたが、環境温度の変化を受容して温度適応システムを駆動する分子機構には謎が多いです。
私たちは細菌やモデル動物を用いて温度適応システムの駆動メカニズムについて分子レベルで研究を行い、最終的には季節の変化に対する適応機構の理解を目指しています。

4.不飽和脂肪酸による神経保護と栄養学的神経疾患予防への応用
日本人が古来より摂取してきた魚には、脳の健康に欠かすことのできない栄養分がたくさん含まれています。そのなかでも、魚油に大量に含まれるn-3系高度不飽和脂肪酸であるドコサヘキサエン酸(DHA)は、他の組織に比べて脳に非常に多く存在し、DHA は神経細胞の細胞膜流動性の改善作用や、抗酸化能や抗炎症作用が報告されたことから、脳の健康維持に必須の分子であると考えられています。しかし、DHA の脳内での役割は完全に解明された訳ではありません。
私たちは、DHAを摂取させたマウスの解析から、DHA を摂取すると脳内で女性ホルモンであるエストラジオール量が大きく増加することを発見しました。このエストラジオール増加は、エストラジオール合成酵素であるCYP19の発現上昇に起因すること、脳内のエストラジオールはけいれん発作に対して抑制的に働くことを明らかにしてきました(Ishihara et al. Sci Rep. 2017)。最近は熱性けいれんモデルマウスを実験に使用し、妊娠期のDHA摂取が熱性けいれんの発症を抑制することを示しました(Kawano et al. Epilepsy Behav. 2021)。また、複雑性熱性けれんという重篤な熱性けいれんを発症した場合、成長後にてんかんを罹患するリスクが増大することが知られていますが、DNAの新生児期の摂取は、熱性けいれん後のけいれん感受性の増大を抑制しました(Kawano et al. Biol Pharm Bull, 2023)。この結果は、DHAを摂取しておくと、熱性けいれん後のてんかん発症リスクが低減することを示しています。

現在、ヒト検体を用いた検討を進めるとともに、DHAの作用について詳細なメカニズムを検討しています。